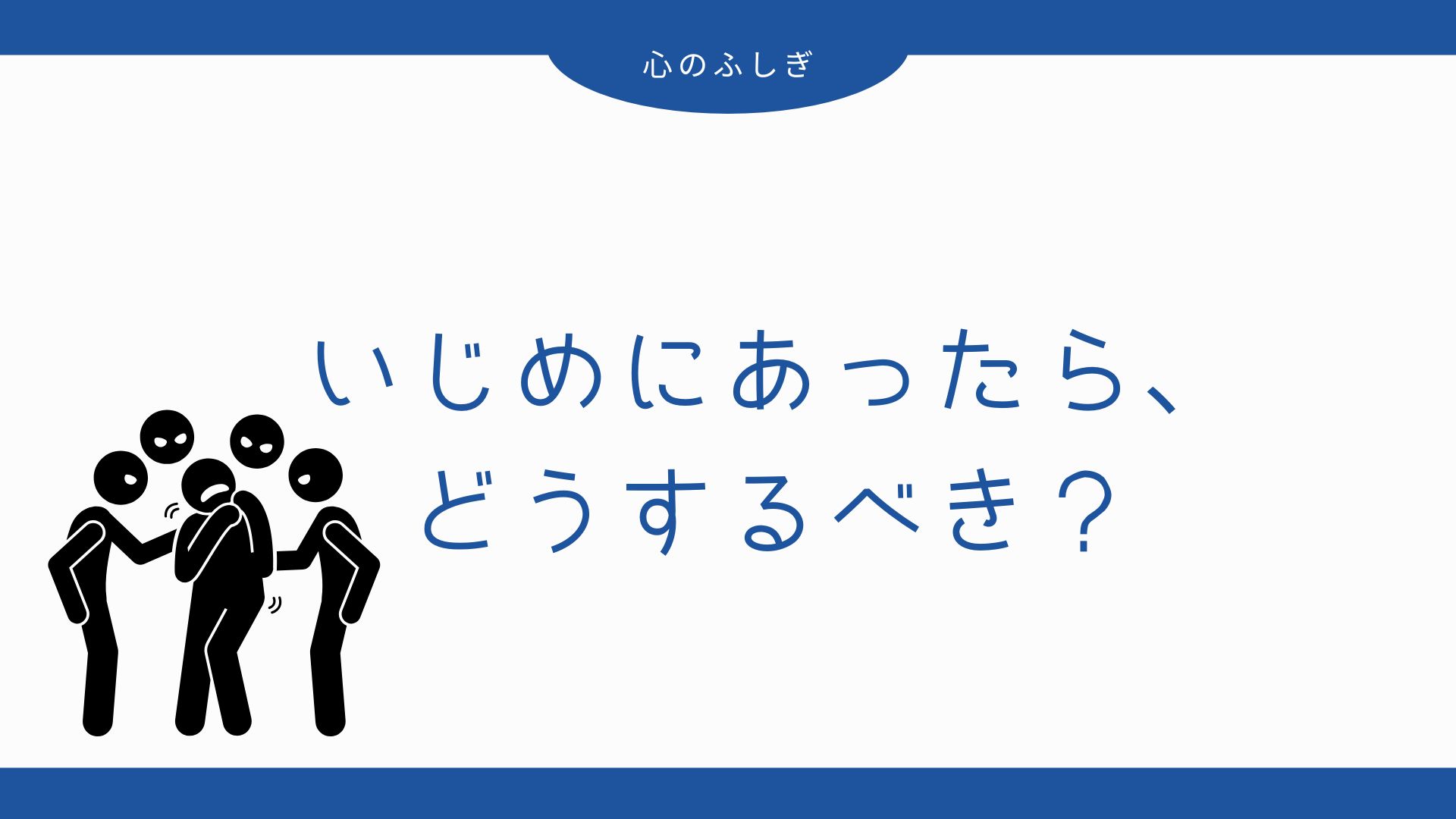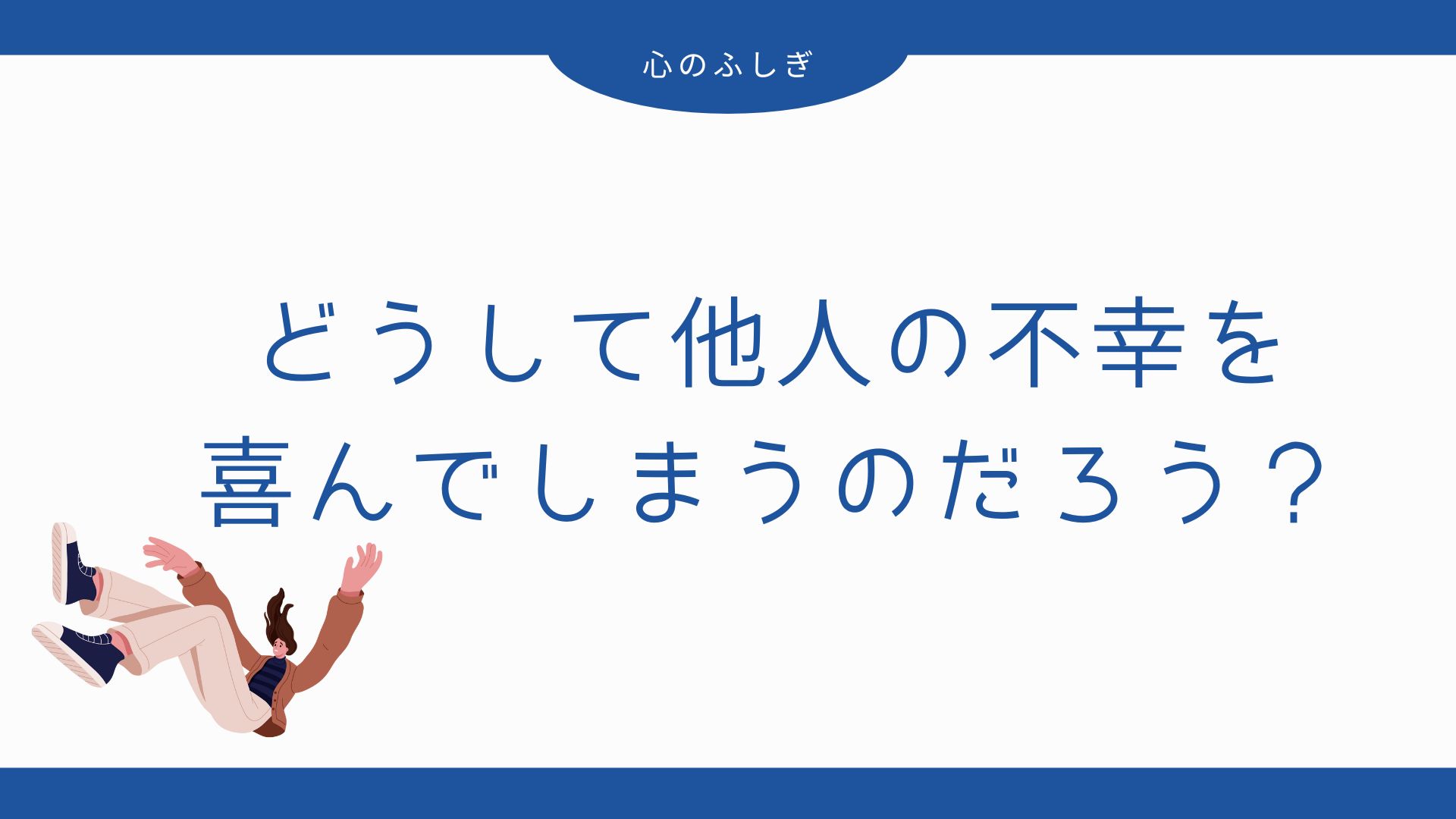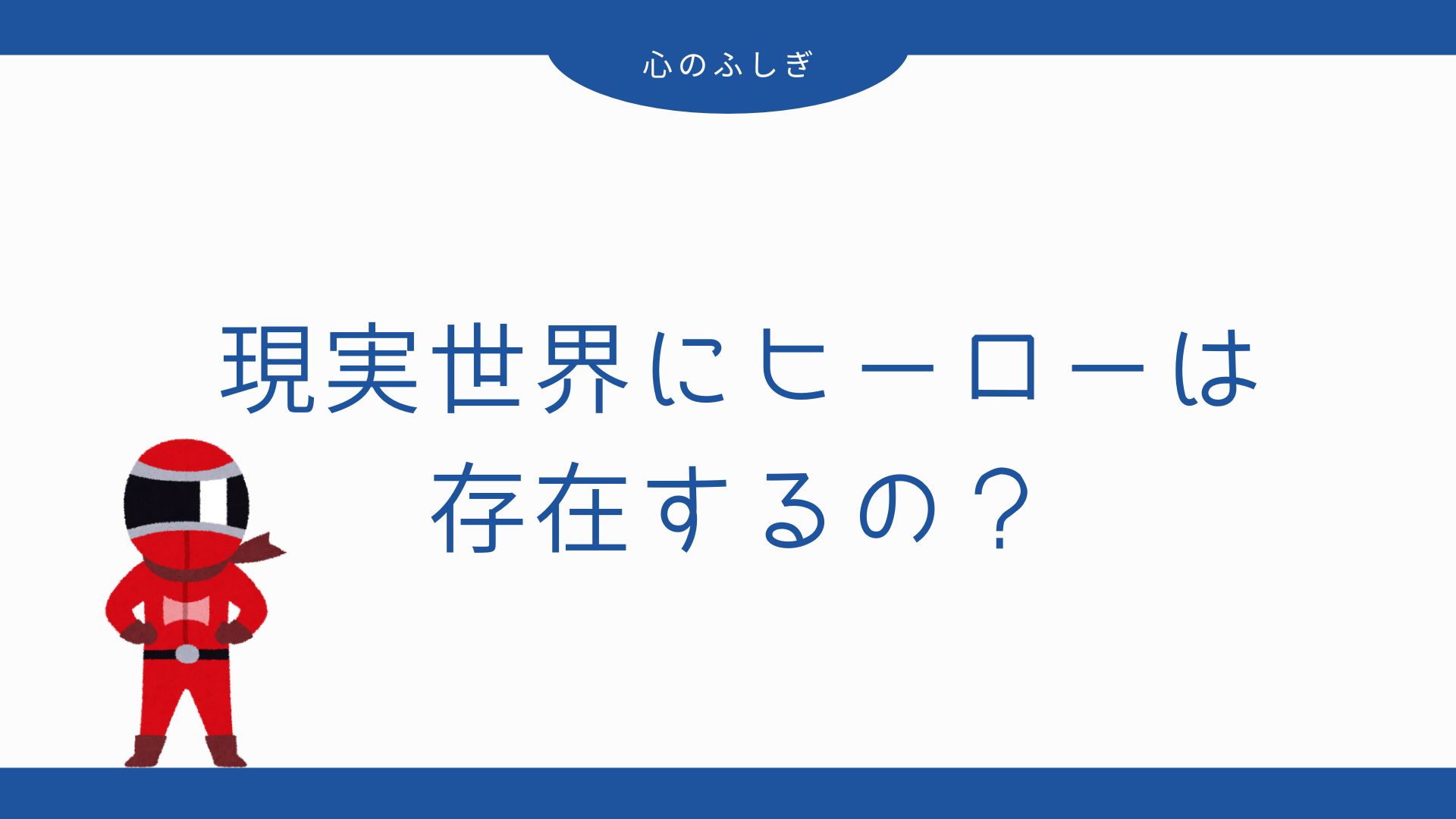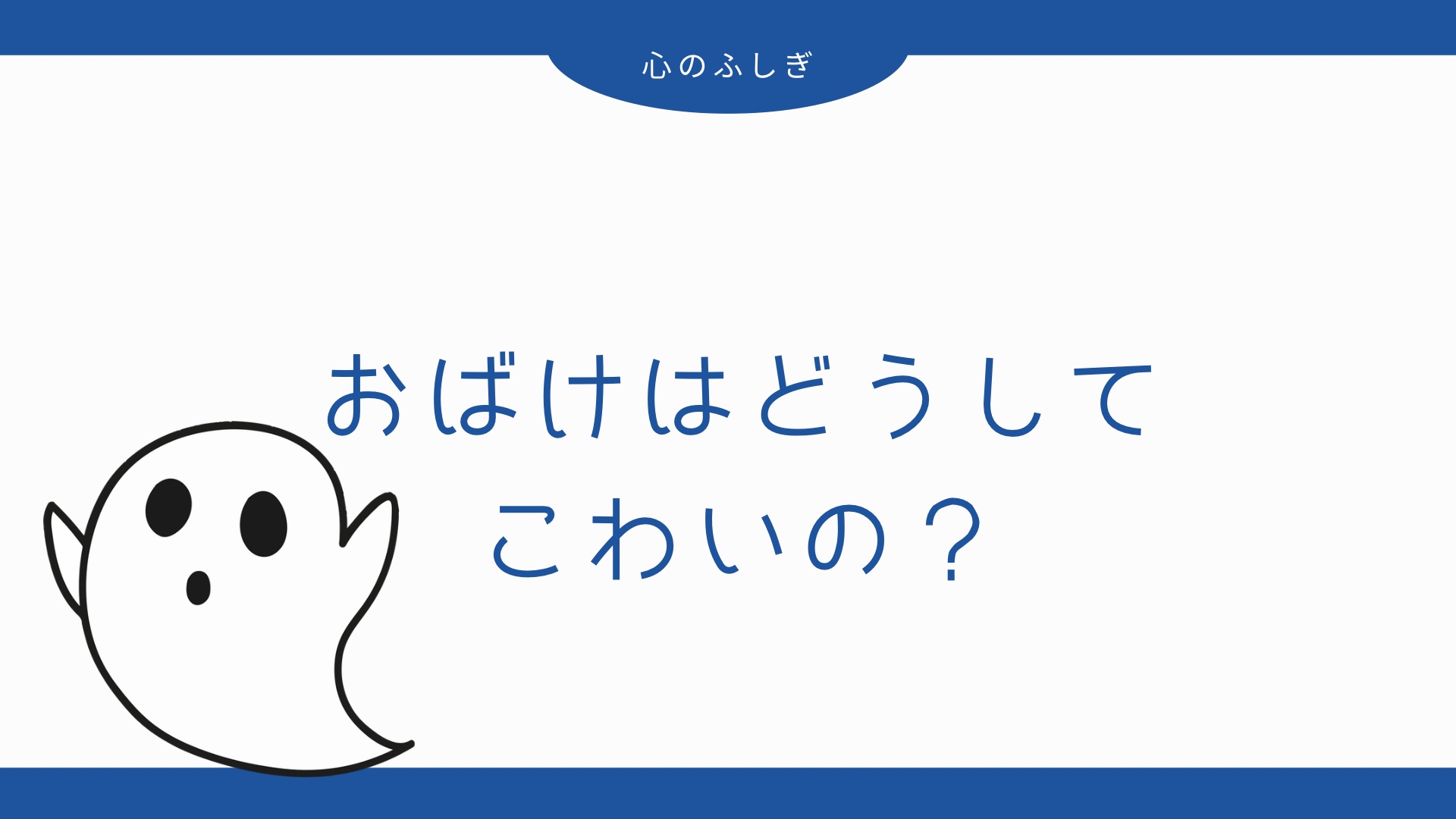なぜ人は他人と比較してしまうのか?その心理をわかりやすく解説!
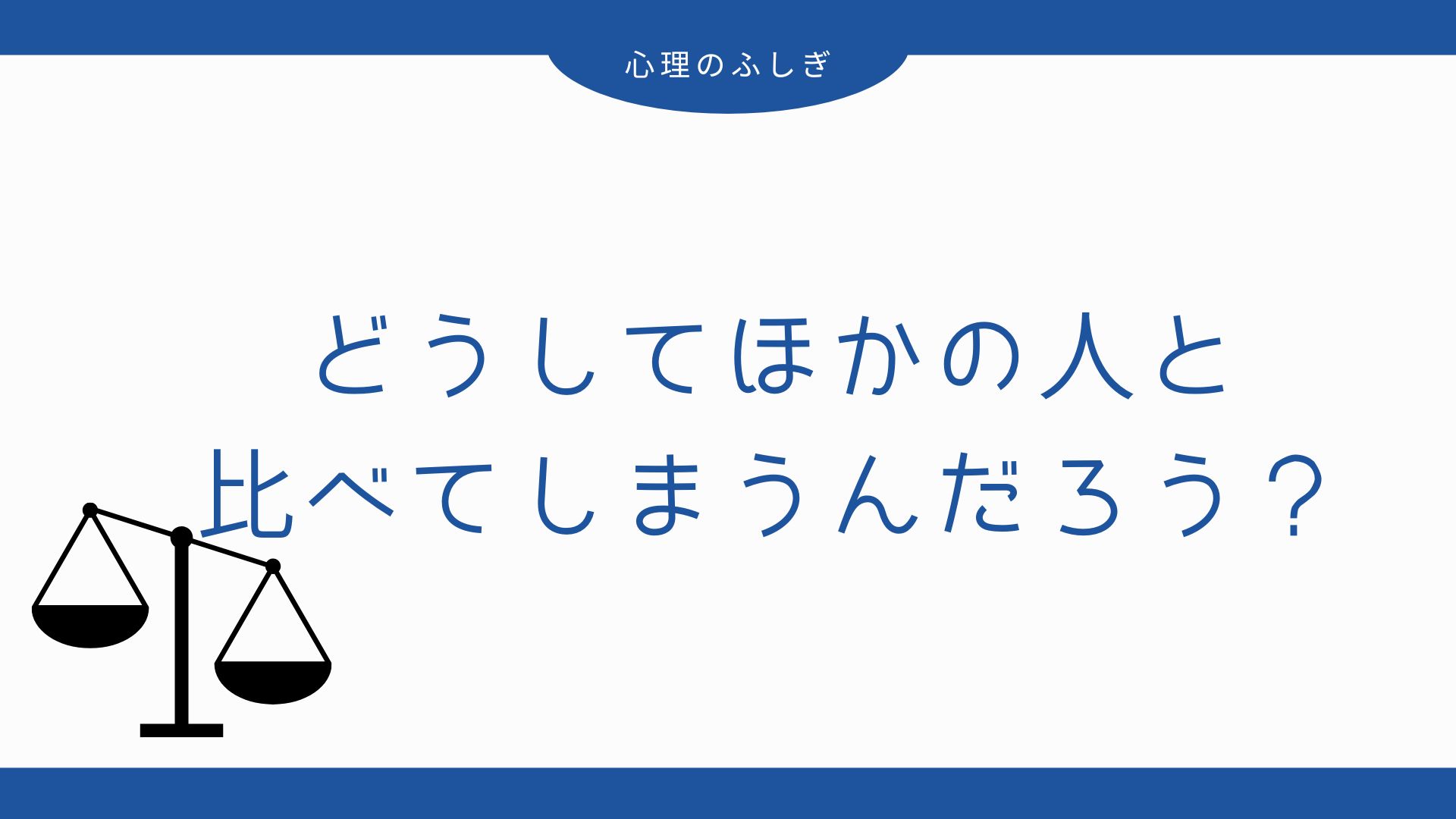
今回のテーマは「なぜ人は他人と比較してしまうのか?」です。
たとえば、友だちのテストの点数が気になったり、SNSでみんなの投稿やフォロワー数を見て自分と比べてしまったことはありませんか?
実はこれ、誰にでもあることなのです。でも、どうして私たちはこうした比較をしてしまうのでしょうか。
その理由を一緒に探ってみましょう!
人が他人と比較してしまうのは、自分の価値や能力を測るための本能。昔から、生き残るために仲間と自分を比べ、行動を調整してきた名残が現代でも働いている。さらに現代はSNSなどで他人の良い面を目にする機会が多く、つい比較してしまう状況が増えている。
比較するのは人間の本能?
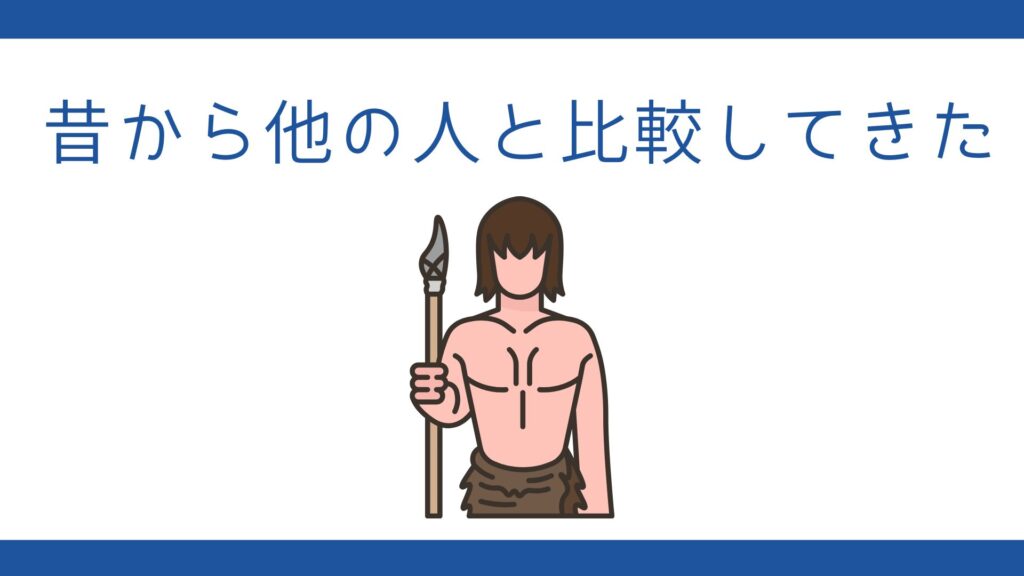
実は、人と比較してしまうのは人間の本能に近いのです。これを専門用語では「社会的比較理論」と呼びます。
心理学者のレオン・フェスティンガーという人が提唱した理論で、「自分がどのくらいできているのか」を測るために他人と比べるのが人間の性質なんです。
たとえば、学校のテストや部活の成績、SNSでのフォロワー数など、みんながつい気にしてしまうのもこの理論が関係しています。
この比較する性質は昔の人類にも役立っていました。たとえば、狩りをしていた時代、自分がどのくらい仲間の中で優れているのかを知ることで、よりよい生存戦略を考えられました。
つまり、私たちが生き残るために必要だった仕組みが現代でも働いているのです。
比較には2つの種類がある
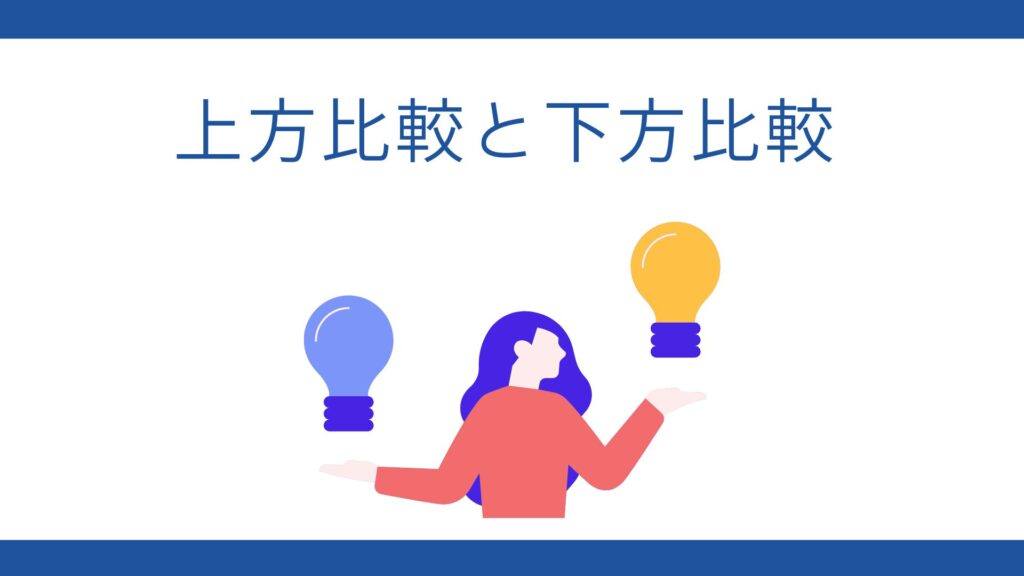
比較には2つの種類があります。一つは「上方比較」、もう一つは「下方比較」です。
上方比較は、自分より優れた人を見て「もっと頑張らなきゃ!」と思うこと。たとえば、クラスで一番勉強できる友達を見て「自分ももっと勉強しよう!」と思うことです。でも、これが行き過ぎると「自分なんて全然だめだ」と落ち込む原因になります。
下方比較は、自分より少し劣っていると感じる人を見て「自分はまだ大丈夫だな」と安心すること。たとえば「この問題ができないのは自分だけじゃない」と感じることですね。ただし、これに頼りすぎると「成長しなくていいや」と怠けてしまう可能性もあります。
このように、比較自体は悪いものではありません。むしろ、自分を成長させるヒントになるのです。
他人との比較が、自分を成長させるヒントになる?
他人と比べることで、自分の強みや課題を明確化することができます。
たとえば、上手にプレゼンする友達を見て「自分にはもう少し練習が必要だな」と気づけたり。友達が得意な方法を参考にしたりすることで、自分に足りない部分を改善できます。
下方比較でも、「自分はこの分野では十分やれている」と自信を持つきっかけになります。
つまり、他人の存在を自分の「学びの材料」として活用することができるのです。
比較と上手に付き合う方法

どうすれば他人と比較しても振り回されずにいられるのか。そのためのポイントを3つお話します。
過去の自分と比較する
他人と自分ばかり比較するのではなく、時には「昨日の自分」や「1年前の自分」と比べてみてください。
たとえば、「昨日より数学の問題が早く解けた」とか、「1年前より長い文章が書けるようになった」など、成長を実感できると他人と比べる必要性がなくなってきます。
SNSの使い方を見直す
現代の比較しやすい環境が原因で、余計に他人と比べてしまうことがあります。
特にSNSでは、みんなが「自分の良い部分」を投稿しているので、そこだけを見て焦ったり落ち込んだりするのは無理もないことです。
でも、SNSの投稿はあくまで「表面の一部」にすぎません。他人の投稿に振り回されるのではなく、「自分は自分」と意識してみてください。
自分の目標を持つ
他人と比べる時間があったら、自分が本当にやりたいことに集中する時間を作ってみましょう。
たとえば、次の試験で「数学を10点上げる」とか「英単語を1日10個覚える」など、小さくてもいいので目標を立ててみてください。
目標に集中すると、他人を気にする時間がなくなってきますよ。
まとめ
本日の話はいかがだったでしょうか。人と比較するのは自然なことですが、大切なのは「その比較をどう受け止めるか」です。
過去の自分と比べたり、目標を持つことで、もっと前向きに成長できるはず。ぜひ、今日から試してみてください!