五里霧中とは?意味・由来・類義語をわかりやすく解説
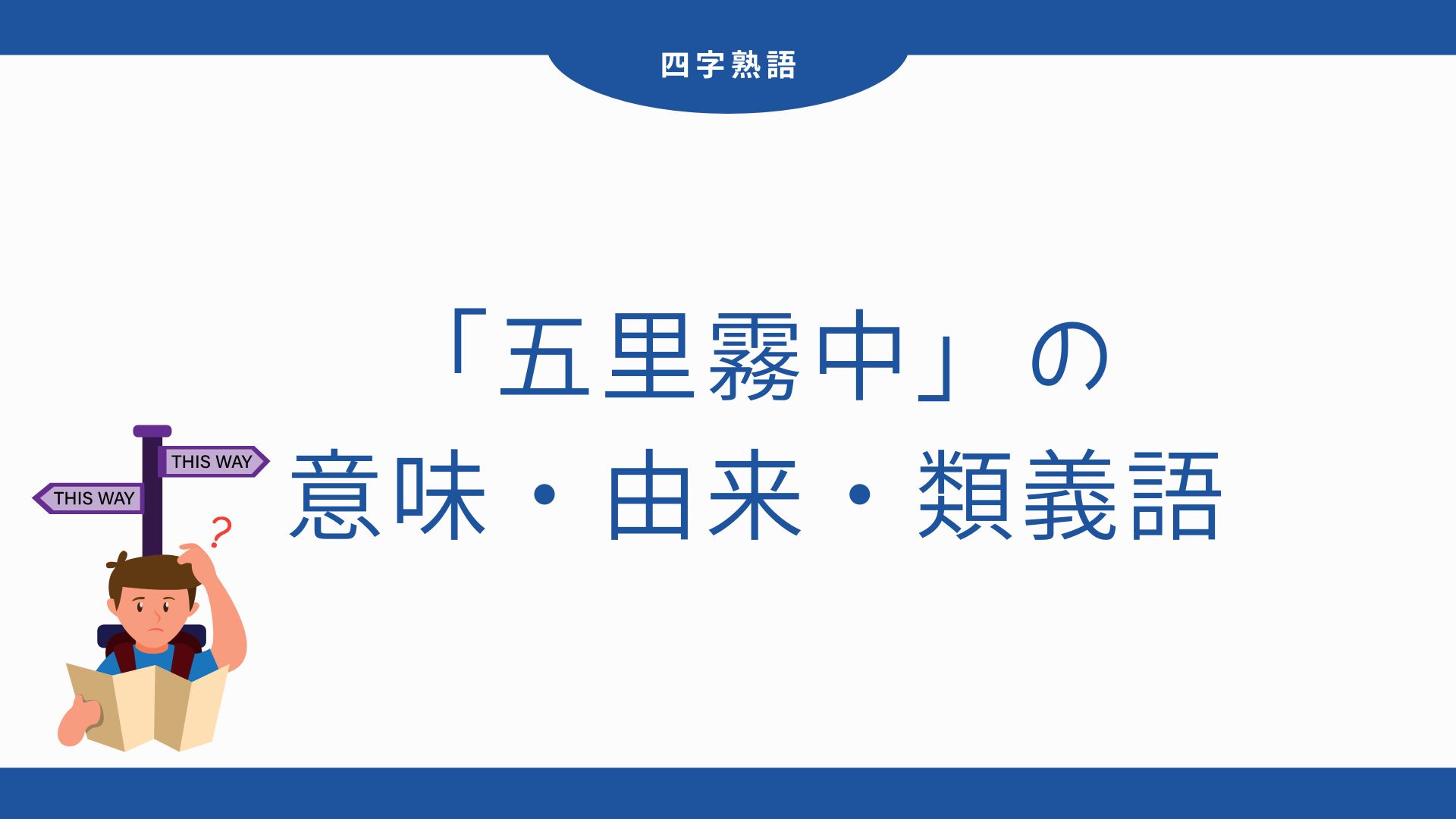
今回は、四字熟語「五里霧中」について解説します。
突然ですが、「手がかりが全くなく、どう進めばいいのか分からない」という状況に陥ったことはありませんか?
例えば、新しいプロジェクトを任されたものの、何から始めればいいのか全く見当がつかないとき。そんなときに使える四字熟語が、「五里霧中(ごりむちゅう)」です。
今回は、この『五里霧中』の意味や由来、そして類義語について、分かりやすく解説していきます。日常生活でも役立つ表現なので、ぜひ最後までご覧ください。
意味 手がかりがなく、何をすればよいか分からない状態
由来 張楷という人物が五里四方に霧を発生させ、人々が迷ったという故事
類義語 「暗中模索」「前途多難」など
意味の説明
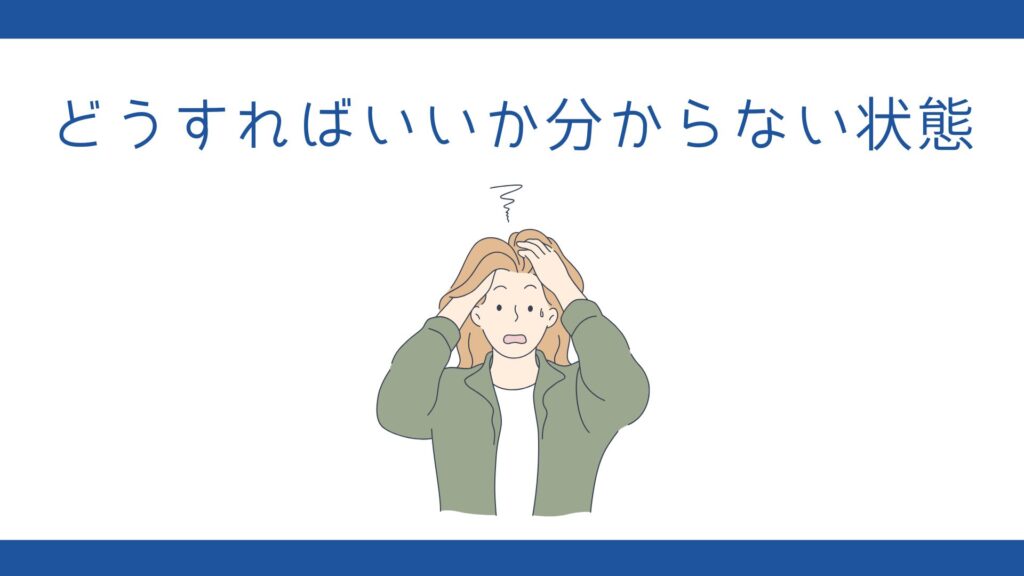
「五里霧中」とは、物事の手がかりがつかめず、見通しが立たない状態を指します。簡単に言えば、「何をどうしていいか分からない」ということですね。
具体的には…
・試験科目がたくさんあり、どこから手を付ければいいか分からないとき。
・新しい仕事を任されたけれど、進め方が分からず途方に暮れるとき。
・行き先を決めずに旅行したら、道に迷ってどうすればいいか分からないとき。
このように、判断の材料がなく、進むべき方向が分からない状況を指す言葉です。
由来や歴史

この言葉の由来は、中国の故事にあります。
昔、張楷(ちょうかい)という人物がいて、五里四方に深い霧を発生させることができたと言われています。
この霧の中に入ると、あたり一面が真っ白になり、方向が分からなくなってしまいました。どこをどう進めばいいのか見当がつかない……
この状況が、今の「五里霧中」という言葉につながっています。
つまり、まるで濃い霧の中に迷い込んだように、何をすればよいか分からない状態を表すようになったのです。
類義語
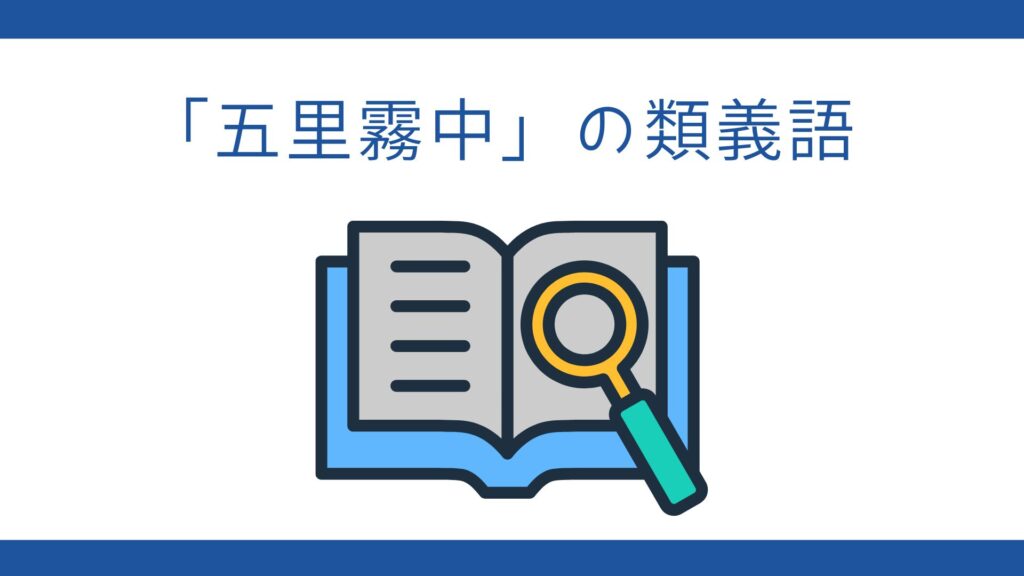
「五里霧中」と似た意味の言葉もあります。
「暗中模索」 手がかりがない中で、試行錯誤しながら探し求めること。
「前途多難」 これから先、困難や障害が多く、どうなるか分からない状態。
「五里霧中」は、ただ迷っているだけでなく、手がかりさえ見つからない状態のときに使うのがポイントです。
まとめ
今回は、『五里霧中』について解説しました。
皆さんが『五里霧中』の状態になったときは、焦らず、まずはできることから一歩ずつ進めてみてくださいね。
